スケ―ラビリティ解決へ向けて、Segwitの次はライトニングネットワーク
ビットコインのスケーラビリティの問題を解決する方法の一つとして有力視されているライトニングネットワーク。それに携わる主要なプロジェクトの開発者たちが今月ミラノで行われたイベントでどのようにマイクロペイメント(少額決済)の仕組みを進歩させ、現在さまざまな所で行われている取り組みを標準化するのかを決定するための話し合いを持った。
ライトニングネットワークとはオフチェーンかつ個人間でビットコインの取引ができるようになる仕組みのことだ。同技術は2015年に初めて提案されて以来、現在少なくとも8つの別々のプロジェクトによって独自設計が進められている。今回のミラノのイベントの趣旨は、ライトニングネットワークの実装方式のうちすべてのプロジェクトが従うべきルールを設定することであり、それによって現在ばらばらに進行するプロジェクトが最終的に相互運用性を持つようにすることだ。
同時進行する8つのライトニングネットワーク・プロジェクトを相互運用可能にさせるために
イベントに先立ち、Lightning Labsの共同創設者Elizabeth Stark氏は、バラバラに開発を進めてきた各プロジェクトは隔週で行われる一連の電話会議とライトニングネットワークのメーリングリストにおける技術的な討論を通して同期を図ってきたと語った。
その他の参加者たちも、作業進捗の情報がどのように共有されるのか詳細について言及している。その情報によると、ライトニングネットワークの初期バージョンは今年の終わりまでには利用可能となる見込みだ。
例えば、Blockstreamのコア技術者であるChristian Decker氏は、この会によってBlockstreamのゴールへ向けて開発を続けられる自信を持つことができたと述べている。「私たちは相互運用性のために必要な全ての詳細事項をなんとか列挙することができました。これによって初期実験段階に結論を下し、そこから得た全ての教訓を組み合わせて前進することができる。」
ただし、ライトニングネットワークには批判もある。ライトニングネットワークとはビットコインをスケールさせるための方法をオフチェーン(ビットコインのブロックチェーンを直接利用しない方法)で提案するものだが、ブロックチェーンを直接利用する必要がある(オンチェーン)と主張するグループもある。
プロトコルの互換性のために採用が決定された実装方式
ブログの投稿に書かれていたように、ミーティングではプロトコルの互換性に関していくつかの意思決定を行い(ライトニングネットワークのアーキテクトであるJoseph Poon氏はそれを『クリティカル・コア・プロトコル』と呼んでいる)、最終的に各実装方式がどのように機能に組み込まれるのかが決定された。
仕様には、2人のユーザー間におけるマイクロペイメント・チャンネルがどのように更新されるのかという「コア・コミットメント・プロトコル」も含まれている。(ライトニングネットワークはHTLCsと呼ばれる暗号化方式に依拠しており、ネットワーク上の決済がいかなる仲介者によっても盗まれることが無いことを保証している。)
ブロックチェーン社の手掛けるThunder方式に取り組んでいるMats Jerratsch氏によって提案された二段階のHTLC方式も決定事項に含まれることになっている。
ミーティングではまた、決済がネットワーク上をどのように行き来するのかという基本的なルーティングプロトコルやその他の実装方式の詳細についても議論を行った。それらの中には、プライバシーのためにノード間のコミュニケーションをどのようにスクランブルするのかというフォーマットや、各チャンネルが詐欺に遭っていないことを監視しユーザーに被害が及ばないようにするためのフォーマットなども含まれる。
今後はビットコインコミュニティのフィードバックを待ってテストを開始
今後については、まずは仕様について最終決定する前に残りのビットコインコミュニティからのフィードバックを求める計画であり、その後数週間を使ってそれぞれの実装方式の相互運用性についてテストが行われる予定だ。
ライトニングネットワーク、相互運用性に向けて大きく前進はCoinPortalで公開された投稿です。
Source: Coin Portal

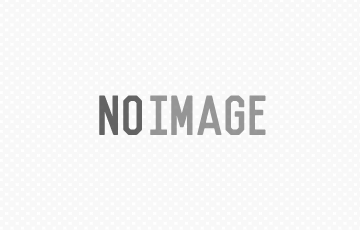
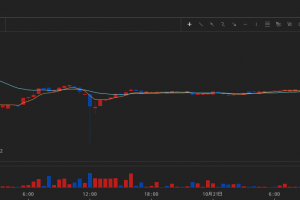

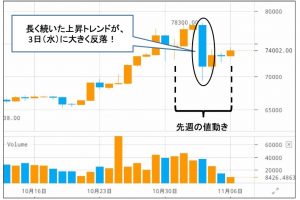

コメントを残す